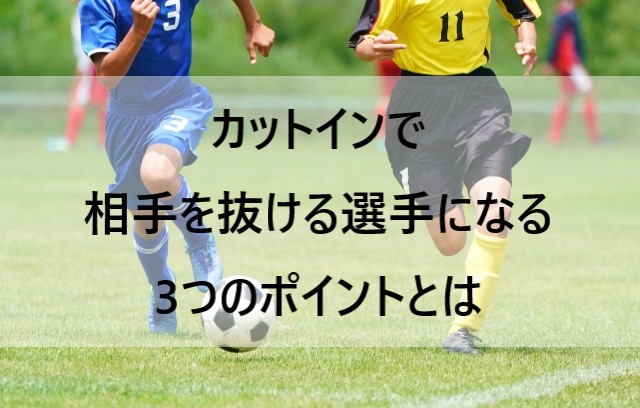カットインで相手を抜ける選手になる3つのポイントとは

ビーレジェンドプロテイン「スポーツ&ウェルネス」の 詳細はこちら
- カットインから相手を抜ける選手になりたい
- サイドから突破してゴールを決められるようになりたい
そう考える選手も、多いのではないでしょうか。
どの時代でも、サイドからドリブルを仕掛けて決定機を作れる選手は重宝されますし、そんな選手に憧れる選手も多いでしょう。
特に近年では、サイドとは逆利きの選手を置き、カットインで中へ切り込んでいく選手が多いです。
カットインを成功させるためには、いくつかポイントがあり、そこを熟知すれば必ずカットインで相手を抜ける選手になれます。
そこで、私自身が経験してきたことを踏まえて、カットインで相手を抜ける選手になる3つのポイントについて解説します。
結論からお伝えすると、
- 相手がボールに触れない角度を熟知する
- 縦にも突破できることを相手に見せる
- 相手の重心をずらす
このようになります。
カットインは
- 角度
- 複数の選択肢
- 重心
この3つが重要です。
それぞれ、具体的に解説していきます。
相手がボールに触れない角度を熟知する
まず、1つ目のポイントが、『相手がボールに触れない角度を熟知する』ことです。
カットインで相手を交わすためには、ボールを運ぶ角度・位置取りが重要になってきます。
意識するべき点は、『相手が足を出してきても触れない角度』です。
例えば、サイドから相手をカットインで交わそうときた場合、ボールを斜め前に出してしまうと奪われる可能性が高くなります。
なぜなら、相手の足とボールの距離が近くなるからです。
では、ボールを真横に出して突破を試みた場合、先ほどより確率は高まりますが、相手が足を出してきたときに触れられる可能性があります。
そのため、カットインで相手を抜くときは、『斜め後ろ』にボールを運ぶことが重要です。
ドリブルに角度をつけるだけで、相手に触られることなく突破できるようになります。
縦にも突破できることを相手に見せる
2つ目のポイントは、『縦にも突破できることを相手に見せる』ことです。
例えば、
- カットインしかできない選手
- カットインも縦にも突破できる選手
この2選手を比較した場合、相手にとっては、より選択肢の多い後者の方が対応が難しくなります。
なぜなら、中なのか縦なのか、どちらにドリブルを仕掛けてくるのか判断できないからです。
カットインの成功率を高めるには、試合中にまず縦への突破を1回2回チャレンジすることで、相手は縦へのドリブルを意識します。
そこでカットインを仕掛けることで、より突破しやすくなるでしょう。
このように、カットインに限らずサッカーでは、『複数の選択肢を持ち、なおかつ相手にも複数の選択肢があると思わせる』ことが重要です。
相手の重心をずらす
3つ目のポイントは、『相手の重心をずらす』ことです。
カットインで相手を突破できる選手の多くが、角度、複数の選択肢、そして相手の重心をずらす能力に長けています。
例えば、
- なにもフェイントなどを使わずにカットインした場合
- 緩急やフェイントを使ってカットインした場合
この2つを比較した場合、相手の重心をずらして突破できる選手は後者です。
- 交わすときに変化を加えられる選手
- 何も変化を加えられない選手
では、大きな差があります。
では、相手の重心をずらすためにはどうすれば良いのか。
それは、『相手の重心を後ろ足にかけさせる』ことです。
例えば、カットインする前に、わざと縦にいくフェイント(ボディフェイントやシザースなど)をしたとしましょう。
すると、相手は一瞬縦への突破を意識して、重心が後ろ足に下がります。
その瞬間にカットインを仕掛けることで、相手はすぐに対応することが難しくなるのです。
シンプルなことですが、相手の重心をずらすことは、ドリブル突破には欠かせない技術になります。
まとめ
カットインで相手を抜ける選手になるためのポイントは、
- 相手がボールに触れない角度を熟知する
- 縦にも突破できることを相手に見せる
- 相手の重心をずらす
このようになります。
重要なことは、
- ドリブルの角度
- 相手に複数の選択肢を持たせる
- 相手の重心をずらす
です。
この3つのポイントを熟知して活かせれば、必ずカットインで相手を抜ける選手に成長できます。
いつもブログ記事を読んでいただき、ありがとうございます。ジュニアサッカー上達塾では、サッカー上達のためにブログやSNSで情報発信をしています。また、サッカー上達のためのDVD教材の販売も行っております。サッカーに関するご質問やお問い合わせ、ブログ記事に対するコメントなどがありましたら、下記のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
メールアドレス:info@kawashima-kazuhiko.com


技術でフィジカルを圧倒する選手が好きなyukito.hです。ラ・リーガを中心に海外サッカーをよく観ます。自分が経験してきたことを踏まえて、サッカーで重要なことを伝えていきます。